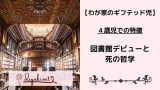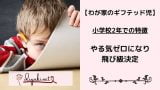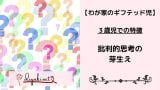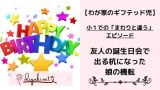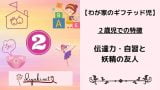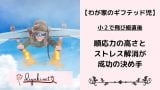ギフテッド児に共通している8つの特徴を、ギフテッド・2E教育専門家で、ご自身もJAPAN MENSAの会員であるMaiさんが、YouTubeで発信した動画を発見した私。
Maiさんは動画内で、アメリカの非営利団体・デイビットソン研究所が発表している「ギフテッド児に共通する8つの特徴」を、ご自分のエピソードと交えて紹介していらっしゃるのですが、ギフテッド児の特徴がもう、ウチの娘のケースに当てはまりすぎ(笑)。
そこで今回の記事では、私が母親の立場で体験した「ギフテッド児に共通する8つの特徴」を、わが家のエピソードと照らし合わせながら、ご紹介していきたいと思います。
【ギフテッド児に共通する8つの特徴】よくみられる特性は、コレ!
- 同学年より数段上の内容を理解する能力がある
- 幼いながらも、驚くほど感情豊かで感受性が強い
- 好奇心が旺盛である
- ユニークな興味やトピックに熱中している
- ユーモアのセンスがある、または大人っぽい
- 創造的な問題解決と想像力豊かな表現力
- 情報の吸収が早く、繰り返し学習する必要が少ない
- 自己認識、社会的認識、グローバルな問題への認識
引用元:YouTubeチャンネル Mai【ギフテッド&2E教育】:【米国の専門機関が発表】ギフテッド児に共通する特徴【IQだけじゃない】
【ギフテッド児に共通する特徴】あるあるだったわが家のエピソード
わが家の場合、「ギフテッド児に共通する特徴8つ」が、娘の特性との該当率100%。もう、あるあるの連続でした(笑)。
では8つの項目について、エピソードを交えながら、ご紹介していきますね。
ギフテッド児に共通する特徴:同学年より数段上の内容を理解できる

娘が文字の読み書きを自分で習得したのは、2歳の頃。
4歳当時の読書量は図書館で借りた本だけでも週30〜40冊、自宅と保育園で読んだ分も加えると、もう測定不能(笑)。
このような背景があったので、ギフテッド児の教育を指導方針に掲げていた私立の一貫校に娘は進学し、小学2年の時、小3・4年の合同クラスに飛び級しました。
「挑戦してみたいから」と、趣味で受けたケンブリッジ英語検定C2/Proficiency(CPE)という、通訳・翻訳者に必要とされる英語検定最難関テストに、最上級のAレベルで娘が合格したのは、16歳の時。ちなみに娘の母国語は、ドイツ語です。
高校の英語の先生よりも、CPEの得点が高かったため、先生から授業参加免除のお許しをもらっていました。
特にCPEテストの準備をしていなかった娘によると、合格の秘訣は、「カーダシアン・ファミリーの動画をよく見ていたから」って、そんなのアリ?!
ギフテッド児に共通する特徴:幼少期に驚くほど感情豊かで感受性が強い

娘の場合、本人の感情の起伏は少なめ。ただ、自分の思う通りに物事を完璧にできないと、非常に強くこだわることがあったので、ときどき手こずりました(笑)。
完璧主義の点以外は、手のかからない子で、むしろ「他人の感情」を、ものすごく敏感にキャッチするタイプでした。
例えば、保育園での出来事を私に解説する際も、テーマの中心は登場人物の感情表現。当事者が身を置いていた状況も鋭く分析して、「なぜその感情表現に至ったのか」という経緯も、彼女なりに推測していました。
また娘は小さかった頃から、一見親切に聞こえるけれど、実は悪意のこもったコメントなどは、すごく敏感に発言内容の真意を感じ取ることに、長けていました。
唯一、娘が感情を抑えられなかった出来事は、「神様の存在」について、宗教の先生に頭ごなしに叱られた体験。
この時の先生の反応は、ギフテッド児が手に負えない大人の態度の典型かもしれません。体験を消化するのに、かなり多くの時間と家庭内での議論が必要となった、苦い思い出です。
ギフテッド児に共通する特徴:好奇心が旺盛

3歳前後の「なぜ・なに」期に突入すると、
- 虫かご・ルーペ持参で外を探索
- 週に2〜3回動物園を訪問し、長時間動物を観察
- 発見した「わからないこと」を本で調べたり、専門家に質問する
という生活形態が、わが家では定着していました。
好奇心がとても旺盛なうえに、注意深い子どもだった娘は、いつでも、どこでも、何も見逃さないので、大忙しでした。
例えば、わが家の裏庭は日本庭園にしていたので、「ししおどし(=竹から水が滴るもの)」があったのですが、娘はししおどしの近くに、トンボがたくさん飛んでくることを発見。
動物園の池付近にも、トンボが多いことに気づいた彼女は、トンボと水の関係を知るために、図書館の本で答え探しをする、といった具合でした。
日常生活の一コマから、あるとあらゆる「なぜ?」を発見し、答えを探求する特性は、成人した今でも変わらない、娘の特徴です。
ギフテッド児に共通する特徴:ユニークな興味やトピックに熱中

通い詰めた動物園では、わが道を行く探求スタイルを発揮していた娘。
同年代の子どもたちが興味を持っていたカワイイ動物ではなく、自分が疑問に感じたワニの潜水時間を調べるため、水槽の前で観察を続けたり、ホッキョクギツネの毛が生え変わる時期の気温を調べ、実際にその場で確認したりといったテーマに、就学前の段階では、夢中になっていました。
ありきたりの「なぜ・なに」ではなく、大人でも即答できないトピックに興味を示すことが、彼女特有のスタイルでした。
娘のおかげで親の私も、自分では思いつかない興味深いテーマに触れる機会に恵まれたので、とても楽しかったです。
ギフテッド児に共通する特徴:ユーモアがある/大人っぽい

頭の回転が速くて、発言内容が鋭い娘のユーモアは、イギリスのブラックジョーク的なセンス。
ですから、まわりがついていけない体験も、数々あったようで、成長してからはその場にいる人と状況を選んで、ジョークを飛ばすようになった気がします。
大人っぽさに関しては、誕生時から「老成していた」赤ちゃんでしたから、筋金入り。
落ち着いていたせいか、娘が「大人っぽい」というコメントは、しばしば耳にしました。
ただ飛び級をしてからは、常に2〜4歳年上の同級生に囲まれて過ごす環境でしたので、小学校高学年以降は、もしかしたらあえて背伸びをして、大人っぽさを意識していたのかな、と母親の立場では思ったりもします。
知能は優れていても、飛び級のために年齢が下で、身体面での発達がまだ子ども状態だった娘は、特に思春期以降、年上の同級生の中でサバイバルする能力が、必要だったはずなので。
これはわが家の娘に限らず、同じくギフテッドの彼女の友人たちも、口にしていることです。
ティーンエイジャーは、特別なことがなくても難しい年代ですしね。
ギフテッド児に共通する特徴:創造的な問題解決と想像力豊かな表現力

小1の時、お友だちの誕生日会で行われた、自分たちで作成した模型飛行機で飛行距離を競うイベント。
工作が得意だったお誕生日パーティーの主役より遠くに飛行機を飛ばし、優勝者用のプレゼントを獲得した娘が、機転を利かせ、主役を引き立てたエピソードは、彼女の創造的な問題解決能力を示す一例ではないかと思います。
また、生活面でのトラブル(物の故障や計画の変更必須)が生じた際の解決方法も、普通では思いつかないようなアイデアをパッと代用案にする能力が、娘は非常に優れています。
「冒険野郎マクガイバー」のライトバージョンとでも申しましょうか(笑)。
想像力についてですが、2歳〜就学前の時期には、妖精のお友だちがいた娘。ほぼ毎日、想像の世界に旅していました。
想像の世界にいるかどうかは、顔つきと態度で明らかでしたので、この世(!)に戻ってきてから、再び話しかけるように心がけていました。
ただし、あちらの世界で何をしていたのかについては、私から内容を詮索することはしませんでした。
文章・ピアノ演奏・クラシックバレエでの表現力は、とても豊かだと、先生方はおっしゃっています(←親バカの上乗せも含みます)。
ギフテッド児に共通する特徴:情報吸収の早さ/繰り返し学習はほぼなし

娘は何事につけ、「一を聞いて十を知る」タイプ。しかも、手に入れた情報を忘れずに記憶することができるので、「繰り返し」には嫌悪感を示すほど。
退屈は敵なので、幼少期には、「簡単すぎず、難しすぎず、繰り返しでもない興味深い課題」に、娘が取り組めるよう、親の立場で気を配りました。

【最近接発達の領域(ヴィゴツキー)】を意識しながら子どもに接することは、頭の賢さ・子どもの健全な自己肯定感・やる気を育てるために、最も大切だというのが、私見です。ぜひ、参考になさってください!
学校での学習内容を筆頭に、ピアノの楽譜・バレエの振り付け・チェスなど、習ってから応用するまでのテンポの速さには、いつも驚かされました(今でもそうですが)。
就学後は、娘が自分から「〜に興味を持ったので、具体的に〜したい」と、提案してくるようになったので、彼女の意思を尊重していました。
例えば、飛び級直後のストレス解消のために、バレエのお稽古の回数を増やしたいなど、親の立場としては、「そんなにたくさんのことに同時にチャレンジするなんて、大丈夫?」と心配もしましたが、本人の心の声を大切にしたことが、結果的に良かったようです。
ギフテッド児に共通する特徴:自己・社会的・グローバル問題への認識

ギフテッド児の場合、自己認識は好むと好まざるとにかかわらず、本人たちが早い時期から直面するテーマ。
どのグループにいても、自然に飛び出してしまうギフテッド児にとって、「他人と違いすぎる自分」を、どのように自分自身で受け止めるかという問題は、ギフテッド特有の最も難しい課題ではないかと思います。
枠からはみ出る自分自身を、肯定的/否定的に理解する傾向は、ギフテッド児が成長する文化環境に、多大な影響を受けるというのが、私の個人的な意見です。
娘が育ったスイスには、目立つことを極端に嫌う文化の特性、つまり日本のような「出る杭は打たれる」風潮があります。
そのせいか、彼女の成長過程で出会ったギフテッド児は例外なく、それなりにつらい経験をしていました。
社会的、またはグローバルな問題についてですが、娘の場合は、社会格差に関する問いを、食卓で私たちとテーマにする機会が多い子どもでした。
スイスでは私立学校が非常に少なく、例えば私立小学校の割合は、全体のわずか10%。
ですからいろいろな場面で、私立校生がやや特殊な存在としてコメントされる体験をしたことも、社会格差が気になる原因になったのかもしれません。
また、日本人の私と、母親が日本人である娘自身も、残念ながら人種差別を幾度となく経験しているため、必然的に社会的な問題に目が向いた影響は、少なからずあると思います。
****************
以上、【ギフテッド児に共通する特徴8点】を、母親の立場で体験したわが家のエピソードを交えて、ご紹介しました。
いかがでしたか? 読者の皆さまのお子さんの性格にも、当てはまることが多かったですか?
子育ては、いつも大仕事ですけど、ギフテッド児の育児には、想像以上の大変さがつきまといます。
わが家での体験エピソードが、少しでもお役に立ちますように♪
天才児が幸せになるためには、知能以外の能力も備えることが、不可欠です。よろしければ、コチラ↓の記事も、ご覧ください。
コチラ↓の2冊は、子育て中に私自身も何度も読み返した本。「ウチの子って、ギフテッドかも?」と、お悩みの親御さんには、心からオススメしたい2冊です。
わが子がギフティッドかもしれないと思ったら: 問題解決と飛躍のための実践的ガイド
ジェームス・T・ウェブその他(著)
ギフティッド その誤診と重複診断: 心理・医療・教育の現場から
ジェームス・T・ウェブその他(著)
関連サイト
デイビットソン研究所(英語):Davidson Institute <Gifted Traits and Characteristics> (閲覧日2022/10/22)
スイス連邦公式サイト スイス連邦統計局(ドイツ語版)<Bildungsinstitutionen>(更新日2022/03)(閲覧日2022/10/22)