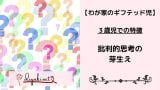子どもに、いつごろから、どんな習い事をさせたらいいのか?とお悩みの親御さんは、多いのではないでしょうか。
娘が幼稚園生だったとき、まわりのお子さんたちが続々とバイオリン・ダンス・英会話などのお稽古に通い始めたと知り、「ウチはこのままでいいのかな」と、私自身不安になったものです。
でも、抱っこ紐付きで私の娘が華々しく(←実は生活感丸出し)大学院デビューしたのは、0歳のとき。0歳で、すでにギフテッドの兆候が明らかな娘の態度から、心理学の専門家たちが異口同音で私にくれたアドバイスは、「小さいうちは、とにかくたくさん遊ばせること」でした。
お経のように囁かれる「幼児教室より遊び」を信じ、育児に励んだ結果、成人した娘自身も大変満足している幼少期を培うことができましたので、わが家で実践した内容をご紹介したいと思います。
【ギフテッド児のお稽古ごと/幼児期】〜スイス在住のわが家の場合〜
- 3歳から小学校入学時までスイミングのみ
- 先取り教育・幼児教室はゼロ。ただし能力を伸ばす育児を自宅で実行
- 子どもが夢中になれる「熱中体験」を親が徹底的にサポート
【幼児期の習い事】掛け持ちが当たり前のトレンドからズレたわが家

ベネッセ教育総合研究所:第5回 幼児の生活アンケート(2015年)によれば、何らかのお稽古事をしている子どもの比率は、
- 3歳児 29.8%
- 4歳児 47.9%
- 5歳児 71.4%
- 6歳児 82.7%
上記のデータは日本での調査結果ですが、娘が育ったスイスでも、子どもが5歳になった途端、周囲のお稽古ブームに火がついた感がありました。
【幼児期の習い事】ギフテッド娘は3歳から就学時までスイミングのみ

習い事の掛け持ちがトレンドだったまわりの流れに背く形で、娘の習い事は3歳のときから小学校入学時まで、週1回のスイミングだけでした。
娘が参加したスイミング教室は、一定の課題をこなせるようになると、次のレベルに進める形態。限られた期間のうちに、目標を据えてトレーニングする、という能力を育てるためには、とても役立ちました。
娘が5歳だったときに、情熱を傾けてスイミングのレベルアップに励んでいた様子は、コチラの記事内にあります。
【幼児期の習い事】教室ではなく自宅で行ったギフテッド育児

学校で習う予定の内容を先取り指導する教室や、音楽や語学の幼児教室へは通うことなく、幼稚園時代を過ごした娘。
ただし、ギフテッド児の好奇心を一生ものの「学ぶ力」に結びつけるために、親ができることは全力でサポートしていました。
例えば、
【文字の習得】
- 娘が自分で文字を習得→ 興味を示す本を与える→ 図書館を週3〜4回利用
- 娘が読んだ本を私も全部読む→ 本の内容をクイズ形式で質問/親子で内容を議論
【数の観念】
親子でのお菓子作りタイムを利用して、数の観念が具体的に身につくように
【興味を掘り下げ、広げる】
動物好きの娘のために、週2〜3回動物園訪問→ 「なぜ」を解明する手段をサポート(図鑑の使い方・動物園での観察・専門家への質問など)
【音楽】
親子でリコーダーを購入→ 保育園と幼稚園で習う歌の楽譜を入手→ 音符に馴染む→ 自宅で親子一緒に演奏
【運動】
動物園訪問を兼ねて、ロープジャングルジムの外遊びを週2〜3回(毎回20〜30分ほど)
以上のように、親子が一緒に何かを体験して、楽しみながら子どもの才能が伸びるような暮らし方を、毎日心がけていました。
娘の「熱中体験」の一例に興味のある方は、コチラ↓の記事をご覧ください。娘が自分で動物園のワニの潜水時間を測ることにチャレンジしたエピソードです。興味が湧いたテーマを、娘がとことん追求できるように、親の私は忍耐力との勝負(笑)。
【幼児期の習い事】熱中体験につながる知的好奇心には甘やかし対応

わが家ではトリプルPの子育て法により、0歳のときから社会生活に必要なルールが身につくように、娘を育てていました。ですから、ルールに関しては、ブレがなく、甘やかすことがない子育てをしたと思います。
逆に、娘が<知りたい/試したい/挑戦したい>と、知的好奇心から興味を持ったことは、すべて受け入れて、親ができるかぎりの対応をしてきました。
子どもが知的好奇心から求めることには、甘やかし専念で育てた、と思っております。
娘が何かに夢中になり始めたら、親としてどうすれば彼女の熱中体験がさらにアツイものになるかと常に考え、実行していました。
「好きこそ物の上手なれ」と言いますが、小学校に入学するまでの幼児期に、子どもが自分自身で夢中になれることを見つけて、好きなことが上達するように目的を据えてチャレンジする経験は、受動的な先取り教育には敵わない学びの本質がある、と娘の成長過程を振り返る私は、確信しています。
まわりの子どもたちが、たくさんのお稽古事や幼児教室を掛け持ちするようになると、「本当にこのままでいいのかしら?」と親御さんも不安を感じることでしょう。
そんな状況にいらっしゃるご家庭にとって、わが家の体験記が少しでもお役に立てれば、幸いです。
わが子がギフティッドかもしれないと思ったら: 問題解決と飛躍のための実践的ガイド
ジェームス・T・ウェブその他(著)
ギフティッド その誤診と重複診断: 心理・医療・教育の現場から
ジェームス・T・ウェブその他(著)