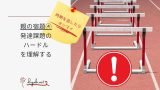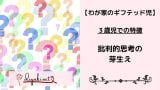わが身の育児を回想しますと、頭の良い子が育つかどうかの分岐点は、なぜなぜ期に凝縮されていると、私は考えております。
ぶっちゃけた話、なぜなぜ期の子どもを親が理想的にサポートできるかどうかで、賢い子特有の思考回路が誕生し、子どもは一生役に立つ「学ぶ力」を使いこなせるようになるのです。
今回の記事では、
- なぜなぜ期の子どもが必要としている親からのサポートは何か?
- 【3歳児】探究力を育てる読み聞かせ6つの秘訣
以上2点を取り上げ、読み聞かせを通じて、一生モノの「学ぶ力」を子どもの心に植え付ける術をご紹介します。
なぜなぜ期の子どもが必要な頭と心の栄養素は2つ

なぜなぜ期真っ只中の子どもにとって、
- 自分の興味の対象を親と共有できること
- 好奇心をそそられた内容を思う存分探求すること
の2点は、いちばん大切な頭と心の栄養素です。
なぜなぜ期の子どもは、「なぜ?」と「見て!見て!」を交互に連発するので、親御さんにとっては大変な時期。
でも、親の無関心さは命の危険に結びつくと私たちのDNAに組み込まれているので、「なぜ?」「見て!」への親の反応が少ないことに子どもは繊細に気づき、探究するよりも親の関心を引くことに情熱を注ぐようになるのです。
親の愛で満たされていないと、学ぶ力のスイッチが入らない状態になってしまいます。子どもの発達過程にとっても、非常に大切なポイントになるので、親子でなぜなぜ期を一緒に楽しむ心構えで、毎日を過ごしていただきたいです。
よろしければ以下の記事の目次の2、【天才児の育て方】愛の絆が頭の良い子をつくるしくみもご参照ください。
発達過程に関する記事は、コチラです。
【3歳児】天才児の特徴・探究力を育てる読み聞かせ6つの秘訣

なぜなぜ期を迎えた3歳のお子さんとの読み聞かせには、図鑑や辞典を取り入れましょう。
お子さんの盛んな好奇心を探求力に結びつけることで、親子の読み聞かせ時間がさらに充実しますよ。
なぜなぜ期に天才児の基盤・探究力を育てる読み聞かせのコツ
- 子どもの「なぜ?」にキチンと向かい合う
- 親が答えを即答できなくても、OK
- 子どもの質問に親子で取り組む。ただし、親が主導権を握りすぎないで
- まず親が「なぜ」を解決する道標をお手本として見せる
- 子どもの「なぜ」を親も楽しみ、回答が見つかったら一緒に喜ぶ
- 見つけた答えをさらに拡大して、新しい「なぜ」につながるように導く
ウチの娘がなぜなぜ期だったころは、どこに出かけるのもメモ帳とハローキティのボールペンを持ち歩き、娘の問いを書き記していました。
娘の質問は独特で、私が即答できたケースは稀。
私が答えを確信していた場合でも、娘には「批判的思考」を身につけてほしいと切望しておりましたので、
- 聞いた答えをそのまま受け入れないで、必ず図鑑や辞典で答えの信憑性を確認する
- それでも疑問が残るときには、さらに自分で解答探しをする
方針で指導していました。
コチラは娘のエピソード。↓
最近はウェブ上で簡単に答えが見つかりますけど、3歳の時点では、問題発見から解決につながる思考回路を作り上げることがメインテーマ。そのためには、子どもが自分で本を開いて情報を確認するプロセスに慣れるように、親御さんは導いてあげてください。
例えば、「雪の結晶の形がどれも違う!」とお散歩中に娘が気づいたときのこと。
早速自宅で本を手にして、雪に関するテーマを目次や索引で探す作業を、すべて子どもに説明しながら行いました。
そうしないと、いずれ子どもが主体となる作業につながらないので、面倒でもひと手間かけてくださいね。
また、娘の質問は専門的な内容が多かったため、幼児用の図鑑だけではすぐに事足りなくなり、小学生向きの図鑑も購入していました。
そのような場合、回答の内容がまだ娘には難しすぎたので、一緒に本を見ながら、まず私が答えを声に出して読み上げる。その後に回答の内容をやさしい言葉で説明する、という2段階プロセスで図鑑を利用していました。
子どもの理解力に適した解説をしてあげると、そこからさらに話が広がり、読み聞かせの面白さがアップしますので、オススメです。
もし、お子さんが飽きてしまうようなら、無理強いは禁物。雪の結晶の写真を図鑑で見てから、再び外へ出かけて結晶の形比べをして楽しむなど、臨機応変に対応してください。
そうすれば、最初から図鑑を使いこなせなくても、時期が熟したら図鑑が大活躍してくれる日が訪れますので、大丈夫。
お子さんの体験の幅を広げるために、例えば<NIKKEI STYLE のライフコラム 子どもの学び>が取り上げているテーマを親御さんがチェックしておき、会話の中で自然にお子さんの関心を引き、親御さんが新しいテーマを投げかける、なんて方法もいいでしょう。
個人的には、なぜなぜ期の娘のおかげで私の雑学が非常に豊かになりまして、娘の存在は高齢出産だった私の日常にきらめきを与えてくれたなぁと感謝しています。
みなさんも、お子さんと楽しい時をお過ごしくださいね!