生まれてから死ぬまでのライフステージで、私たちはある一定の年齢に特有なテーマに直面しながら、人生を歩んでいきます。
例えば、トイレにひとりで行けるかどうか。
幼稚園生活をスタートするときは、まだときどき失敗することがOKでも、小学校に入学するときにはひとりできちんとトイレに行けないと、学校という社会の中で学ぶことに集中するのが、むずかしい状況になります。
心身の健康に恵まれた人間が通り抜けるライフステージにある、特有な課題の克服に成功するのか、それとも失敗するのかが、その後の人生の展開に大きく影響を与えてしまうので、発達課題のハードルについて、理解を深める必要があります。
そこで、今回の記事では、以下のポイントについて解説をしていきます。
- 発達課題とは
- 人生における8つの発達段階と各段階のキーワード・概要
- 発達課題のハードル
- 発達課題が克服できないと人生の歩み方に天地の差
- 各年齢期での発達課題:子どもをサポートする親がクリアすべき課題
【天才児の育て方】発達課題とは?:定義の主要メッセージは、コレ!

エリクソンの心理社会的発達の理論が提唱する内容は、以下の通りです。
- ヒトが生まれてから死に至るまでのライフステージには8つの発達段階がある
- それぞれの発達段階には、克服するべき課題がある
- 発達課題をクリアできないと、そのステージで停滞したまま。クリアできたら、次の段階に進める
- 次の発達段階に進んだばかりのときには、いつも困難がつきまとう
【天才児の育て方】人生における8つの発達段階:キーワード・概要

多少の個人差や文化の影響はありますが、健康に恵まれた地球上の人類はみんな、同じようにライフステージを通過し、それぞれの段階がしかける課題に直面します。
エリクソンは、それぞれの発達段階にある課題の克服に成功もしくは失敗することが、私たちの人生に与える影響を、以下のように比べています。
乳児期:基本的信頼 対 不信
課題:自分を守り、養ってくれる親の存在を感じ、信頼する。
幼児前期:自律性 対 恥・疑惑
課題:トイレコントロール。
幼児後期:積極性 対 罪悪感
課題:外の世界へ探検に出て、新しい体験をする。
学童期:勤勉 対 劣等感
課題:学校で学ぶこと。
青年期:同一性 対 同一性拡散
課題:自分はどんな人間なのか?
前成人期:親密さ 対 孤立
課題:性を通じて、他人と親密な相互関係を持てるか?
成人期:生殖性 対 自己没頭
課題:次の世代を育てる。
成熟期:統合性 対 絶望
課題:これまでの人生をふりかえる。
【天才児の育て方】発達課題のハードル克服は子どもの成功に不可欠
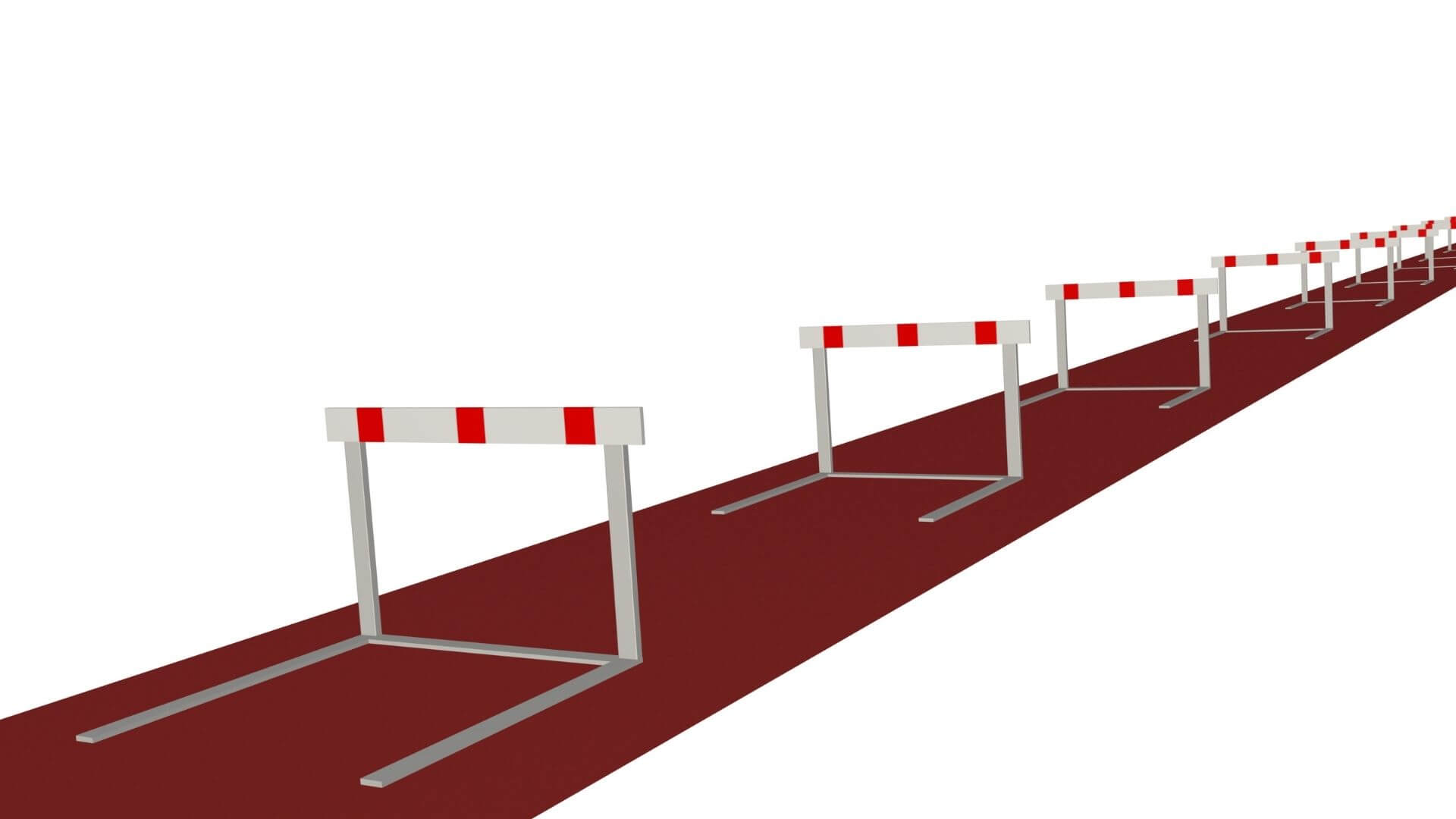
私たちは成長する過程で、
- 身体のなかから生じる変化:身長・体重・ホルモンの影響
- 社会での体験にもとづく変化:学びを通じて身につけたスキルによる影響
という内外の原因から、常に構造や機能の変化を遂げつつ、生きています。
発達課題の克服に挑む私たちにとって、やっかいなのが内外の原因が引き起こすアンバランス。
私たちがどの発達段階にいるのかは、身体の内側から生じる原因が否応なしに決定します。
だけど、次の発達段階に進めるかどうかを決めるのは、体験から習得した能力。
問題を克服するスキルが足りないと、身体だけはすでに次の段階に達しているのに、経験不足から欠けている能力のせいで、前の段階に立ち止まったまま、というアンバランスな状態になるのです。
ヒトは、課題の克服に失敗した発達のステージで停滞してしまうので、人生の早い段階でつまずいてしまうと、その後の発達段階にある課題が、どんどん山積みになって増えていきます。
次のステージの課題をクリアするためには、前の課題を克服して身につけたスキルが必要となるので、「じゃあ、その次の段階にひとっ飛び」と、未解決の課題を避けることはできないのです。
【天才児の育て方】発達課題が克服できないと人生の歩み方に天地の差
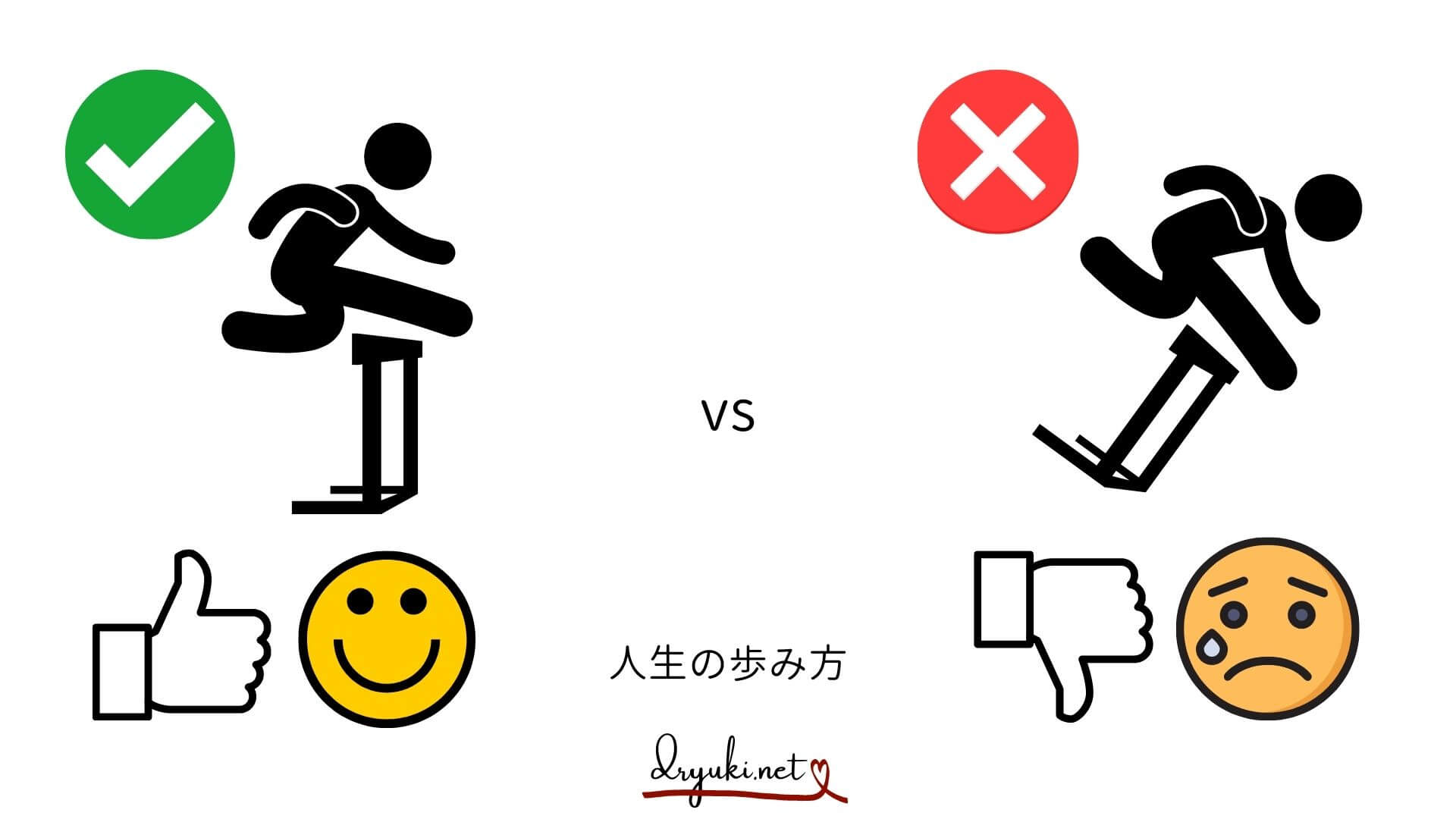
発達課題は、
と、課題の克服ができたかどうかにより、人生は大きく左右されます。
「ウチの子ってもしかして?!:天才児の特徴」でも記したように、生まれつきの頭がどんなに良くても、高い知能を社会でうまく活用する能力が身につかないと、せっかくの才能も宝のもちぐされ。
恵まれた才能を最大限に生かして、子どもが満足のいく人生を歩めるように、それぞれの成長時期で親はどのような姿勢で子どもをサポートするべきなのか、というポイントを次のパートで見ていきましょう。
【天才児の育て方】各年齢期での発達課題:親がクリアすべき課題

課題を無事にクリアできるかどうか、チャレンジするのは子ども本人ですが、カワイイわが子の熱烈サポーターである親御さんが、どのように応援すれば子どもの力になれるのか、その内容を以下にまとめました。
【天才児の育て方】親の課題:丈夫な愛の絆の作成/0〜1歳半

言葉でなにも言えない赤ちゃんが相手なので、とにかく赤ちゃんの気持ちを態度から的確に読むことが大切。
赤ちゃん専属の「気分予報士」になるつもりで繊細に赤ちゃんに接しましょう。十分なスキンシップも、愛情を互いに感じ合う大切なポイントです。
親の繊細な対応と深い愛情は、親子のあいだに丈夫な愛の絆を育ててくれます。
【天才児の育て方】親の課題:基礎知育とプレしつけ/1歳半〜3歳

子どもが自分でできることを実感できるように、時間がかかっても本人にチャレンジさせる、そして失敗することがあっても叱らない姿勢で、子どもに接しましょう。
子どもは、まだ自分から積極的に興味を引く対象とコンタクトをとることができないので、まわりの環境にある物や人に関心が持てるように親がサポートしてあげることが、次の発達段階で学びの原動力・探究の冒険に出かけるためのベース作りとなります。
また、子どもに基本的な生活のリズム(食事・睡眠)が身につくように心がけること、そしてあいさつやお礼の言葉がすんなりと出るように導くことも、集団生活のスタート準備として必要です。
【天才児の育て方】親の課題:応用知育としつけ/3歳〜6歳

外の世界へ積極的に冒険に出かけたい、だけど知らないことだらけで少しこわい、という欲求のはざまで揺れる子どもは、ネガティブな感情や疲れから回復するために、親の元に戻ってきます。
親の役目は、子どもがエネルギーを充電できるようになぐさめと安らぎを与え、子どもが探検で見聞きし感じとった内容を、興味深く聞いてあげること。
そして、再び子どもが気持ちよく冒険に出かけられるように、「ここにいるから、いってらっしゃい」と送り出しましょう。
また、子どもの探究心をフルに生かすため、外の世界への探検から得た知識を広げて深めるためのサポートをすることも、大事な課題のひとつ。
この発達段階のときに、
- 親から離れて外の世界へ探検に行く
- 興味を持ったことにチャレンジする
- 失敗と成功のプロセスをくりかえし体験する
という学びのステップを子どもが会得できれば、頭の良さを発揮して人生で成功するための七つ道具を手に入れるようなもの。
小学校に入学する前のこの時期に、学びのステップが子どもに定着するかどうかが、子どもの未来に大きな影響を及ぼすのだと心して、子どもが自分で課題のハードルを超えることができるように、お手伝いをしてあげてください。
なお、本格的な集団生活がスタートする前に、ルールを守る・きちんとあいさつをするという点をしつけることも、親の責任です。
子どもが自分でできることは進んで行うように、日頃から家庭内で担当するお手伝いの役割を決め、うまくできたらほめてあげましょう。
【天才児の育て方】親の課題:ベッタリはオサラバ/6〜9歳

子どもが学校生活に集中できるように、起床時間や持ち物の用意、身支度に必要な時間などの生活習慣が整う環境を、家庭で作りましょう。
子どもの自立が目的なので、親が代わりに問題を片付けるのではなく、「〜の準備はできた?」と積極的に声をかけるかたちでサポートをします。
学校という新しい環境は、それぞれ異なる価値観で育ってきた子どもたちが集まる場所。
家庭の価値観は、家庭の数だけありますので、当然、子ども同士のいさかいも生じます。
カワイイわが子が他の子ともめている、さぁ大変!とすぐに親が仲介に入ることは、けっしてしないように。
子どもが伝えてくるトラブルの内容には真剣に耳を傾け、落ち着いてもめごとの展開を見守りましょう。
見守る親の心情は、子ども以上につらいものになるかもしれませんが、大抵の場合、子ども同士で解決策をみつけられるものです。
今の時期に自分でもめごとを解決する練習をしておかないと、いつまでたっても子どもの社会性が育ちません。
成長すればするほど、子どもが直面する問題も深刻で複雑になるので、できるだけ早いうちから自分でもめごとを解決する姿勢が、子どもにとっていちばんためになることなのだ、ということを忘れないで。
【天才児の育て方】親の課題:グループを把握/9〜12歳

グループの存在は、子どもの健全な発達に不可欠です。
ただ、この年齢期の子どもたちは、グループ内でのおきてに従わなければグループから追放、みたいな過激な流れになりやすい傾向があります。
念の為、子どもと親しいメンバーが誰なのかを、親は把握しておきましょう。ただし、付き合いを見守るスタンスで、友人へのコメントは控えます。
万一、子どもが深刻な問題に巻き込まれているようなら、子どもへの批判は抜きで、「あなたのことを本当に心配している」と親の気持ちをストレートに伝えましょう。
仲間への批判をすると、グループのプレッシャーを受けている子どもは、本音では親に相談したいのにできないジレンマにおちいるので、注意が必要です。
グループのメンバーと自分を比べることで、子どもが劣等感や悩みを抱えやすくなるので、子どもの話の聞き役を務めることも、親の大事な課題。
自分は必要とされている、と子どもが実感できるように、家庭内では積極的にお手伝いをさせるのもいいでしょう。
普段はグループの話をしたがらない子どもでも、親と一緒に作業することが、悩みを打ち明けるきっかけになったりします。
子どもが「私もこんな人になりたい」と目標にできるような生き方をしている大人と、学外の活動で出会う場があれば、理想的です。
【天才児の育て方】親の課題:嵐が去るのを待つ/12〜15歳

ママさん・パパさんにとって、きびしい季節の始まりです。
この時期の子どもは、
- 親から距離をおく
- 親はなんにつけまちがっている
- 親はとにかくみっともない
と、強烈にアタックしてきます。親にとってホントにしんどい、嵐の季節です。
子どもが強気な態度で親を挑発してくる機会が増えますが、子どもの心の中はものすごく傷つきやすいときなので、親が感情的な態度をとらないように、心がけてください。
あんなにかわいかった子どもなのに、突然別の生き物になってしまったのでは、と錯覚さえおぼえますが、この発達段階で親がすべきことは、以下の3点です。
- 定期的に、家族が一緒に過ごす時間をとる(朝食か夕食は必ず一緒になど、ご家庭のスケジュールに合わせて続けることが大事)
- 子どもの話をひたすら聞く(評価・批判コメントはタブー)
- 健康的なケンカをする(自分の気持ちを伝え、相手の気持ちを受け止める。同じ意見になる必要はなく、ニュートラルもしくは仲直りでシメのスタイル)
また、子どもの身体が大人になる際、身体にどんなコトが起きているのか、そして身体が成熟したら気をつけるべきことはなにか、という性についての話をすることも、親の重要な義務なので、子どもにきちんと説明をしてあげましょう。
【天才児の育て方】親の課題:信頼できる相談相手/15〜18歳

このお年頃の子どもにとって、親はハッキリ言ってどうでもいい存在(涙)。
だけど、緊急事態におちいったとき、または今後の人生を左右する選択に迫られているときには、子どもは必ず、親を頼りにしてきます。
子どもが相談事を持ちかけてきたら、「待ってました!」とおしゃべり攻撃をしてはいけません。
子どもの相談にのるときには、
- 自分の意見を正直に伝える。子どもの意見と食いちがう点があっても、隠さない
- 子どもの意見には敬意を払って対応する
という内容をバランスよくとりまぜて、会話を進めるようにしましょう。
まとめ【天才児の育て方】④発達課題のハードルを理解する

発達課題のハードルをうまく超えることができるのか、それともつまずいてしまうのか、課題の克服はまさに私たちの人生模様を決定する分かれ目になります。
特に、新しい発達のステージに入ったばかりの子どもは、慣れない状況で次の課題を克服するためにかなりのエネルギーを要するので、親に当たってくることもしばしばあります。
温かい目で忍耐強く、一歩引いた場所から子どもを応援していきましょう。
子どもはそっけない素振りしか見せてくれませんが、熱烈サポーターのママさん・パパさんの存在は、きちんと子どもに届いて、人生を前向きに歩んでいくための大事な心の支えになります。
大事なポイント:子どもの頭を良くしたい親の宿題④ 発達課題のハードルを理解する
- 発達課題とは、私たち人間が生まれてから死ぬまでの、ある特定の年齢期のときに直面する課題
- 身体的な成長と、経験から身につけるべき能力の発達が並行して進んでいけば課題がクリアできるので、社会のメンバーとして安定した人生を歩むことができる
- 発達課題をクリアできないと、自分の才能を社会で発揮することがむずかしくなるため、ヒトの心に劣等感・不満・絶望感がつのる
- 課題は、子どもが自分でクリアすべきこと。親はサポーターの立場で、一歩引いたところから応援
参考文献
文部科学省「3. 子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題」(閲覧日:2021年8月6日)
Orenstein, G. A., & Lewis, L. (2020). Eriksons stages of psychosocial development. StatPearls [Internet]. (閲覧日:2021年8月6日)





