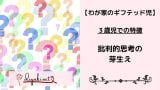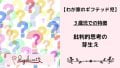批判的思考を持ち合わせなければ、素晴らしい才能に恵まれた天才も凡人で終わってしまいます。
自分のアイデアを活かし、平凡から突出するための秘訣・批判的思考は、子どもの頭を良くするための原動力なのです。
批判的思考とは?
自分が疑問を持ったら、まず情報を集める。そして手に入れた情報による答えが本当に信頼できるのか、自分で検証して答えを出す。のちに再検証が必要と思われる場合には、全経過を繰り返す、という思考プロセスのことです。
- 「何だろう/なぜだろう?」という疑問を持つ
- 疑問を説明している情報を集める
- 情報の内容はどのような根拠に基づいているのか/情報発信者は誰なのかを調べて評価
- 手に入れた情報の真偽を自分で検証してみる
- 判明した結果から、謎解きの答えを見つけ出す
- 答えが判明してからも、常に新しい情報を敏感にキャッチし、必要であれば上記のプロセスを繰り返す
わが家のギフテッド娘が、なぜなぜ期にどのようにして批判的思考を身につけたのか、その様子を記したエピソードの記事も、よろしければご覧ください。
批判的思考を重要視するスイスの教育システム:わが家の体験談
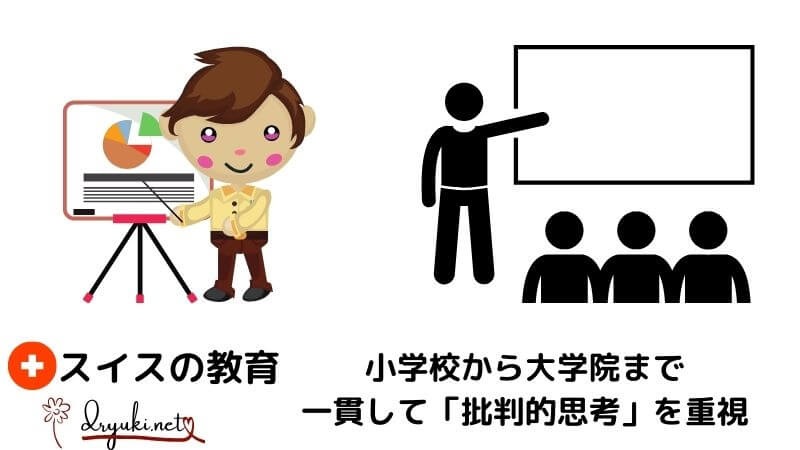
スイスの小学校からギムナジウムまで:娘の体験を通じて見た批判的思考重視教育
娘の母校は、OECDから独創的で豊かな教育方針を認可された学校のひとつで、「子どもたちが卒業するときには、次の時代を切り開くためのスキルを身に付けていることが学校の使命」だと、先生方が一丸となって取り組んでいることが、保護者にひしひしと伝わってくる環境でした。
小学校高学年から、とにかくプレゼンテーションの連続。パワーポイントを利用する発表と、モデルなどを自分で組み立てて材料を作成するプレゼンが、7対3くらいの割合で行われていました。
授業全体の流れとしては、
- 扱っているテーマの中から、自分で課題を決める
- その課題をプレゼンテーションする必要性を、まず先生に訴える
- 認められた課題の「専門家」として、問題提議/現在まで判明している情報/情報の問題点を掲げ、自分なりに検証。その結果をプレゼンテーションとしてクラス全員の前で発表
- プレゼンテーションでは、ただ黙って聞くのではなく、積極的に質問することで、発表者の検証結果を討議
- 発表者は、投げかけられた質問に回答し、全員が納得のいくような答えに導く
- 問題点が残った/新たに発生した場合には、解決策が見つかるように再度調査
という流れで、発表内容だけではなく、発表時の態度も採点されるシステムになっていました。
スイスの大学/大学院で:私が体験した批判的思考重視の教育のあり方
私が大学で体験した講義/セミナーの内容も、上に述べたギムナジウムまでの方法と同じく、批判的思考を重視する姿勢でした。
学士・修士課程のときには、研究結果があまり明確に実証されなかった科学論文をあえて選び出し、自分がその論文の著者であるかのように、全力で研究内容を擁護する「発表者」になりきる。そして、「傍聴者」は検証結果の粗探しを嫌な姑のようにする役に分かれて、練習を重ねる辛いセミナーまでありました。
しかも、同じ学年同士で練習していては、あまちゃんだという理由で、あえて博士課程の学生が傍聴者の役をあてがわれ、まだか弱き学士・修士課程の学生のプレゼンテーションを叩きに出てくる、というスゴ技まで使われていました。
傍聴者からの強烈な批判に、発表者が泣き崩れることもしばしばあったほど。ええ、これが心理学科の実態です(笑)。
とても厳しい体験ですが、このようにして培われる能力は、現実社会で自らの才能を発揮して、満足できる人生を歩むためには、とても役立つ経験だと実感しています。