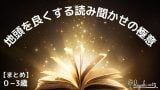英語教室は、幼児に人気の習い事のひとつ。でも、就学前には家庭でしっかり、国語である日本語でまず「ことばを育てる」ことが大切。
ことばが賢さの基盤になるワケ、そしてことばを毎日の積み重ねで育てるために、天才児育児で私が実践していたことをご紹介します。
【ことばが持つ5つの力とは?】英語早期教育、ちょっと待って!

【ことばの力】考える力/表す力/知識としての力/感じる力/想像する力
参照サイト:文部科学省 第1 国語力を身に付けるための国語教育の在り方
ことばは、人と社会をつなぐカギ。
- 自分の考えを、ことばで表現する
- ことばから知識を身につけ、能力を形成する
- ことばを通じて、相手に自分の感情を伝える
- 他人のことばから、相手の気持ちを理解する
- ことばによる表現で、他人とコミュニケーションを図る
など、家庭・学校・社会生活のすべてで、「ことば」は人の生活の要となる役割を果たしています。
【ことばの育て方】子どもにとって親は最高のお手本兼練習相手
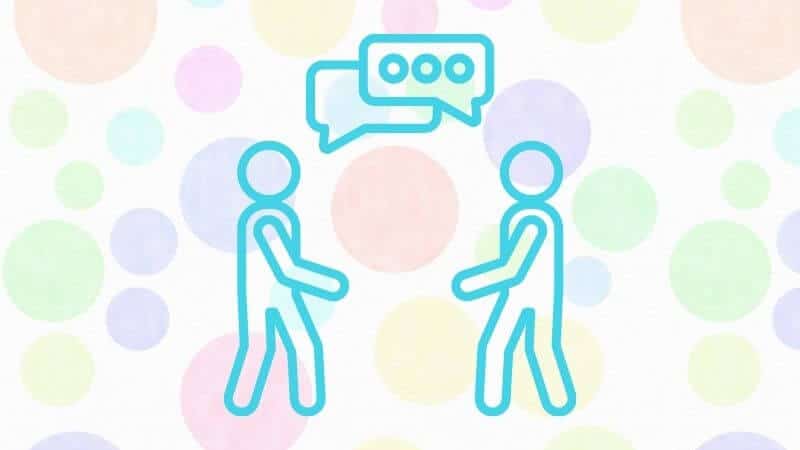
ここで親御さんに注目していただきたいのは、ことばが描写するものは、「考え」「要求」「感情」といった抽象的なものであること。
子どもは1歳前後になると、自分を囲む周囲の「もの」には、名前があると気づきます。
「もの」の名前は、コミュニケーションにおいて分子のようなもの。自分の頭に浮かんだ抽象的なアイデアや気持ちを表現するための最小道具です。
子どもは成長する過程で、これらの道具の使い方、つまり「どのように『もの』の名前を組み合わせると、相手に伝わるのかな?」という方法を、親御さんとの交流で身につけていくのです。
- 自分の考えを的確に伝えるには、どうすればいいのか
- 感情のニュアンスを、どのように表現すればいいのか
- 相手のことばに込められた意味は、何なのか
- 自分の要求と相手の意見の折り合いをつけるには、どう交渉すべきなのか
これらのことばを育てる練習は、お子さんひとりではできないこと。会話のキャッチボールがなければ、子どもはことばの使い方を学ぶことができませんからね。
ですから、毎日の暮らしの中で
- 親が<心のときめきメガネ>を装着して子どもに接する
- 親子で<注意の共有>を繰り返し体験する
という生活態度を取り入れ、親が子どものことばを育てる環境を整えてあげることが、大切なのです。
<心のときめきメガネ>と<注意の共有>についてはコチラの記事をご覧ください。
幼児期にことばを育てないと、どうなる?

素晴らしいアイデアを他人に伝えるための架け橋は、「ことば」です。どんなに素晴らしいアイデアも、「ことば」を通じて相手に理解してもらえなければ、何の役にも立ちません。
そして、社会生活を送るうえでも、「ことば」は他者との関係を調整する際に、不可欠な要素です。
幼児期に「ことば」が上手く育たないと、
- 自分の要求を他人に理解してもらえない
- 自分の感情を相手にわかるように表現できないので、態度で表す(攻撃的・内向的)
といったことから、失敗体験が続き、自己実現はおろか集団生活でも問題行動が目立つようになります。
【早期教育の英語】母国語のことばの基盤がなければムダで無意味!

ベネッセ教育総合研究所:第5回 幼児の生活アンケート(2015年)によれば、「英語」は幼児に人気の習い事のひとつ。
グローバリゼーションが進む世の中で、カワイイわが子にできるかぎりのチャンスを与えたい。そのためには、幼いころから英語を身に付けることが大切、とお考えになる親御さんが多いのでは。
ですが・・・
「英語を早く始めればネイティブライクになれる」というのは誤解である・・・特に日本にいながら教室で英語を学ぶ場合は、相当首尾よく構築されたカリキュラムでない限り早期の学習は無意味となる。
引用元:慶應義塾大学学術情報リポジトリ 年齢が第二言語習得に与える影響:早期英語教育のあり方を問う 水田愛、古石篤子 p.8
とあるように、英語の早期学習が実を結ぶ可能性は低いのです。
あなたのお子さんと同じ年頃のお子さんたちが、こぞって英語教室に通いだすと、「ウチの子も始めないと、ダメかしら」と焦るお気持ちは、私も体験したのでよくわかります。
けれども、しっかりしたことばの基盤がない段階で、外国語のレッスンを始めたところで、時間とお金がムダになるだけ。
お子さんのためを思うなら、就学前の幼少期だからこそ、周囲に流されず、お子さんの「ことば育て」に時間と愛情をかけてあげましょう!
コチラは幼少期の習い事についての記事です。
【ことばを育てる生活習慣】天才育児で実践した「実を結ぶやりとり」

0〜3歳の子どもとのコミュニケーションの取り方は、読み聞かせのコツをまとめた記事内でも、ご紹介しています。
ムリなく楽しく有益に、親子で会話をするためのヒントになると思いますので、よろしければコチラの記事もご参照ください。
【ことばを育てる会話のキャッチボール法】成功に導く7つのポイント

- 子どもに注目し、親子間で心が通じ合う状況を作る
- 話を振るのは親。でも、話す主役は子ども
- 短い文章と丁寧なことば使いで話しかける
- 会話の際、これ/それ/あれ/どれの指示語は避け、具体的なことばを選ぶ
- 子どもが耳にすることばのバリエーションが豊富になるように(単語の種類/色/形/サイズ/用途など)
- 5W1H(いつ/どこで/誰が/何を/なぜ/どのように)を軸に話を引き出す
- 感情(子どもが体験を通じて感じたこと)は、親のコメント抜きで受け止める
親戚やお友だちのお宅で体験した出来事や、幼稚園でのエピソードなどのほかにも、子どもの目に映る日常生活はキラキラ輝いているので、ことばを育てる話題には事欠きません。
上記でご紹介した7つのポイントを心がけながら会話のキャッチボールを行うことで、ことばだけではなく愛情の絆もさらに育ちます。
小学校から高校まで、才能あふれるお子さんたちが数多くいた娘の母校の生徒さんたちの成長ぶりを振り返ると、就学前に、
- 家庭でしっかりしたことばの基盤を育てる
- 子どもが夢中になれる遊びを体験させる
という2点は、すくすく育った賢い子たちの共通点。
毎日のふれあいから育てたことばは、就学後のお子さんに、大きな実をもたらします。
ぜひご家庭で取り入れてみてくださいね♪
子どものネガティブな感情表現に向き合う方法は、コチラの記事に記載しましたので、よろしければご参照ください。
コチラの記事ではわが家で実践していた「ことば遊び」をご紹介しています。