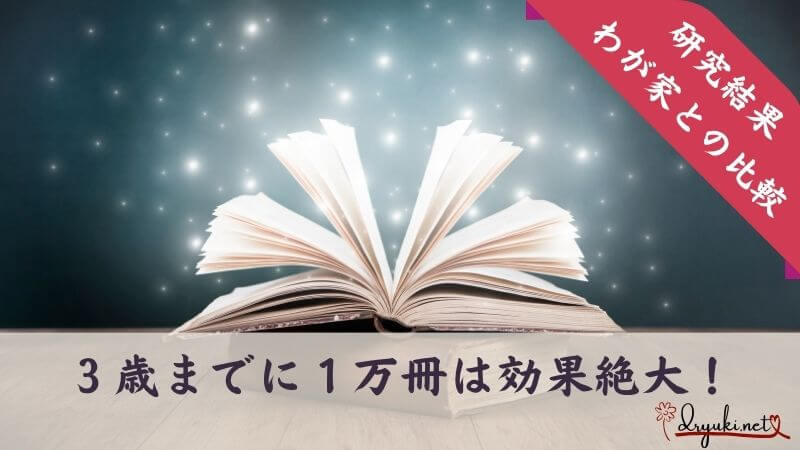本の読み聞かせは、子どもの知育で話題になるテーマのNo.1。
「3歳までに1万冊の本を読み聞かせること」が、子どもの頭を良くするための大切なカギとして、よく取り上げられていますよね。
そのせいか、「3歳までに1万冊」を目標に掲げていらっしゃるご家庭の実践レポートや、読み聞かせにオススメの本の紹介に関する豊富な情報が、インターネット検索でたくさん見つかります。
けれども、幼児期に日常的な読み聞かせをしてもらった子どもたちの、その後の成長ぶりを明らかにした研究結果の情報は、ほとんど見つからない状態。
これは、非常にもったいないことです。
なぜなら、日常的な本の読み聞かせは、親である私たちが意識して毎日の生活に取り入れ、実行し続けることで大きな実りをもたらします。
でも、子育て中の親御さんの毎日は、忙しくて大変。
そのような生活テンポの中で、お子さんのために読み聞かせの時間を費やし、しかも長期間継続するためには、「毎日の読み聞かせが子どもの成長に与える好影響」の研究結果を具体的に知ることが、とても大切だと私は思うのです。
少なくとも私には、結果が伴うのかはっきりしないことを、毎日続けるエネルギーは、ありません。でもね・・・。

「本の読み聞かせ」効果は絶大だから、毎日続けるべき!
そこで今回の記事では、以下のテーマについてお話したいと思います。
読み聞かせが生んだ効果:
- ティーンエイジャーを検証したドイツの研究結果
- 天才児認定を受けた娘への読み聞かせを研究結果と比較
【天才児を育てる】本の読み聞かせの効果:ドイツの研究結果

ドイツでは2007年から毎年、「読み聞かせ」に関する様々なテーマをStiftung Lesen(読み聞かせ推奨財団)・ドイツ鉄道・Die Zeit(ドイツ最大の週刊新聞社)が共同で研究し、その検証結果をレポートしています。
ここでご紹介する内容は、その研究結果のひとつです。
- 研究「本の読み聞かせが子どもの発達にもたらすこと」(2011年)
- 研究の対象になった子どもたち:10〜19歳(505人)
研究データが国の現状をできるだけ正しく把握するように、研究の対象になった子どもたちの性別・年齢・母親の最終学歴レベルの分布率が、ドイツ全土で占めるそれらの割合にできる限り近い形を取るように構成されています(あぁ研究的表現)。
→つまり、「読み聞かせ」に関するドイツでの実情を把握した研究だということです。
参考サイト:Stiftung Lesen Vorlese-Studie 2011:Die Bedeutung des Vorlesens für die Entwicklung von Kindern
(閲覧日2021年10月19日)
幼少期の読み聞かせから青少年期にバランスの良い成績優秀児が育つ!

| 毎日読み聞かせ | 週1〜6回読み聞かせ | 読み聞かせなし | |
| 読書が楽しい | 74% | 48% | 37% |
| 最低週に1度は読書 | 87% | 67% | 64% |
| 平日読書にあてる時間 | 58.5分 | 42分 | 33.9分 |
| 週1でスポーツ活動 | 79% | 63% | 54% |
研究に参加した10歳から19歳の子どもたちの回答で興味深いのは、すべての点において「毎日の読み聞かせ」が生んだ効果が、抜きん出ていることです。
読書への喜び、頻度、読書にあてる時間が、「毎日読み聞かせがあった」グループで突出しているのはもちろんのこと、スポーツを定期的にしているティーンエイジャーの割合が、読み聞かせの頻度とともに高くなっています。
| 読み聞かせあり | 読み聞かせなし | |
| 14歳以降・本離れ率 | 9% | 24% |
| 17歳以降・読書が辛い | 19% | 43% |
特に14歳以降は「読書離れ」が起きやすいと言われるのですが、週に1度以上の「読み聞かせ」を体験した子どもは「本離れ」しにくいと判明。
また、すでに17歳以降の研究参加者の場合でも、幼少期の「読み聞かせ」体験が読書に対する苦手感を抑えることが明らかになっています。
そして更なる読み聞かせの特典があります。
読み聞かせをしてもらった子どもは、学校の成績が良い
読み聞かせ体験者の成績は、言語の科目だけではなく、数学・スポーツ・音楽でも、読み聞かせ体験のないグループの子どもたちより優秀であると、研究で判明。
*統計分析で、読み聞かせあり/なしグループの子どもたちの成績を比較したときに、両グループ間に「偶然とは考えにくい」差が出たということです(これも研究ことば)。
【体験談】飛び級児を育てたわが家の読み聞かせ習慣と効果
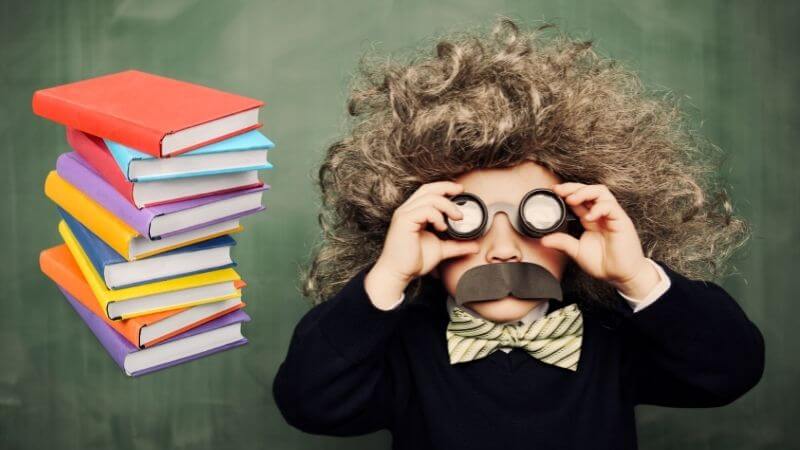
- わが家での読み聞かせ:0歳から毎日
夜寝る前だけではなく、いつも「本にすぐ手が届く」環境で生活し、1日数回に分けて読み聞かせをしていました。 - 娘は読書好き:本の虫に育つ(毎日最低1時間は読書)
本を読んでいる間は、パラレルワールドに行って戻ってこないほど、本の世界に浸っています。 - 定期的にスポーツ:週平均7回以上、クラシックバレエのレッスン
小学校入学時にスタートしたバレエを、現在まで継続しています。 - 14歳以降の本離れなし
このころから、小説は英語で読み始めていました。
娘は15歳の時に、C2 Proficiencyを最上級のAレベルで取得したので、ネイティブレベルで英語を使いこなせます(私の英語を笑うのやめて、と切実な母からの願い)。 - 17歳以降も読書をこよなく愛する
「静かだわ…」と思うと、本を読んでいる娘。 - 3歳までの娘の読書量=1万冊以上
2歳過ぎたころから、1日30冊以上は本を読んでいたように思います。
お気に入りのぬいぐるみの代わりに、娘はいつも本を手にしていました。
クリミナル・マインドのDr. リードの本の読み方は、娘を彷彿とさせます(笑)。娘は静かに本のページをめくりますが、読むテンポはそっくり。
わが家の場合、「1日何冊」という読書ノルマを掲げることなく、娘と楽しみながら一緒に本を見ていたら、どんどん読み聞かせが膨らんでいった、という感じです。
何事にも新鮮な興味を示した娘のおかげで、大人になった私が目を塞いでいた、私たちの周りにあるさまざまな奇跡に再び着目する機会ができて、私はもう楽しくてたまらなかったのです。
読み聞かせというより、娘とふたりではしゃいで本を手に過ごした時間という方が合っているかもしれません。
逆転合格東大生と天才児の娘への読み聞かせ方は完全一致
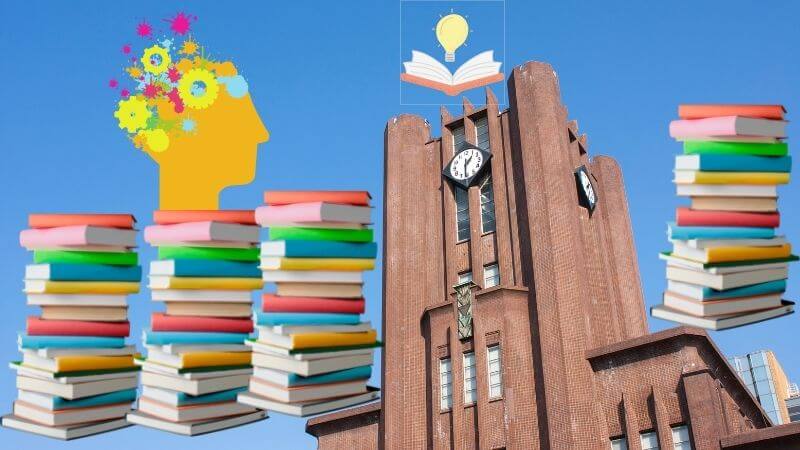
自分が楽しみながら子どもに読み聞かせをして、子供も存分に楽しませるというスタイルは、PRESIDENT Onlineに掲載された、現役東大生ライター・布施川天馬さんの記事によると、東大に逆転合格した家庭の読み聞かせ極意だそう。
記事の中で紹介されている親御さんたちの読み聞かせ方法は、私自身のことかと思うほどで、完全に一致。
思わず笑ってしまいましたが、東大生と天才児への読み聞かせ方法が重なっているのは、とても興味深いことだと思います。
東大生と天才児を育てた「子どもの頭を良くするカギ」、親子で楽しむ読み聞かせを、ぜひ毎日の生活に取り入れて、お子さんの才能を最大限、伸ばしてあげてくださいね。
関連サイト:PRESIDENT Online 「本の読み聞かせ方が全然違う」わが子を東大に逆転合格させる親のマネできそうでできない技 (閲覧日2021年10月19日)
まとめ:本の読み聞かせは子どもの才能を多彩に開花させるためのカギ

- 幼少期の本の読み聞かせは、子どもの発達に効果あり
- 読み聞かせの効果は、17歳過ぎてからも顕著
- 読み聞かせの頻度が高いほど、子どもの成長に好影響
そしていちばん大切なこと!

読み聞かせは、親子で楽しむ毎日の習慣にしましょう!