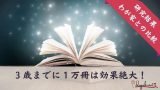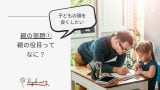「便利なスマホやテレビを子どもに見せてもいいわよね?」と思っている親御さん、ちょっと待って!
幼い頃から長時間スマホやTVを視聴すると、子どもの発育に悪影響があると科学研究で判明しているのです。
子どもがスマホやTVなどを使用する際の時間の目安【年齢別】
- 0〜3歳未満 使用させない
- 3〜5歳 30分/1日
- 6〜9歳 45分/1日
- 10歳 1時間/1日
オススメしている年齢別の使用時間目安は、スマホ・TVが子どもたちに与える影響を研究している専門家たちが、現在までに検証されたデータをもとに推奨している内容です。
東北大学加齢医学研究所の研究:長時間TV/ネット/ゲームの脳への悪影響

東北大学加齢医学研究所の竹内准教授と川島教授の研究グループが、小児の縦断追跡データを収集・分析し、長時間のTV/インターネット/ビデオゲームの使用習慣は、数年後の言語力や脳の形態に悪影響を及ぼすことを発見、論文で報告しています。
スマホやテレビなどを使用する育児が子どもに良くないワケ

子どもがスマホ/TV画面からの情報を消化しきれない
子どもは情報を受け止め、整理し、消化する時間を必要とします。
けれども、画面からの情報は、色・音声・映像などが目まぐるしく変化するので、子どもは情報の消化不良を起こすのです。
長時間のメディア画面使用は、落ち着きのなさ・騒ぐ・睡眠障害など、子どもの問題行動につながることが、研究で報告されています。
親子間での相互体験よりスマホ/TVが優先される危険性
スマホやテレビの媒体が近くにあると、子どもばかりか、大人もつい、媒体の画面に注目してしまい、親子で一緒に楽しむべきだった時間をダラダラ過ごしてしまうなんてことが起きやすくなります。
けれども、頭の良さを発揮して生きるために、子どもは人として大切な非認知能力も、同時に身につける必要があります。
例えば、文部科学省では
- 健康な心と体
- 自立心
- 協同性
- 道徳性、規範意識の芽生え
- 社会生活との関わり
- 思考力の芽生え
- 自然との関わり、生命尊重
- 数量や図形、標識などへの関心・感覚
- 言葉による伝え合い
- 豊かな感性と表現
以上10点を、「幼児期の終わりまでに育ってほしい幼児の具体的な姿」として、幼稚園・保育園・認定こども園での教育活動の指針にしています。
これらの能力をお子さんが身につけるためには、家庭内での親子のふれあいの中で、一緒に体験したことに関して互いの意見を交換し合い、楽しく過ごす時間が不可欠です。
文部科学省:「幼児期の終わりまでに育ってほしい幼児の具体的な姿(参考例)」
(閲覧日2021/11/27)
ちょっと話がそれますが、3歳までに1万冊の本を読み聞かせるから、天才児が誕生するわけではなく、脳が活発に形成される幼少期に、1万冊の本を読破できたほど親子で親密に、楽しく過ごす時間を持つことができたから、頭の良い子に育つのではないかと、私は思っております。
子どもがスマホ/TVを使うときに親が注意すべきこと

いつ、どれだけ、何を見ていいのか、先に親が決めておく
一度スマホやテレビのOKが出ると、子どもは巧みなトリックを使って、どんどん視聴時間が長くなるようにあの手この手を使ってきます。
親がはっきり「ダメです」と線を引くことは、子どものためになる苦い薬。一度決めたことから親御さんが簡単にブレないように、気をつけて!
ごねるお子さんを黙らせたいからと、子どもがしたがることをすぐに許していると、あっという間に親子の攻防戦がエスカレートしますからね。
子どもが見るスマホ/TVの内容チェック、もしくは一緒に見る
就学前のお子さんでしたら、できれば親御さんも一緒にスマホ/TVを視聴することを、私はオススメします。
わが家では、番組を見終わってから物語の内容について、娘が疑問に思った点とか、納得いかなかった登場人物の態度など、いろいろ私とおしゃべりすることで活発な意見交換をしていました。
一緒に視聴していれば、映像から受け取った情報を親子で共有して楽しむことができますし、私が娘に物語の内容を質問してクイズにする、または娘に物語の要約を語らせるなどと、一石二鳥プラスアルファで便利な使い方ができました。
休憩時間が必要なことを忘れずに
映像が子どもに与えるインパクトは、とても強烈なので、視聴後は必ず休憩を取らせるように。
ウチではテレビ視聴後はおやつの時間にして、おやつをいただきながらゆったりと、今見た内容についておしゃべりをするようにしていました。
大人が見本になるように
子どもにはスマホ・テレビの利用制限をするのに、親だけは好き勝手に使っているとなると、「もっと見たい」ゴネゴネ問題が発生しますので、お気をつけあそばせ。
スマホ・TVをごほうび/罰の対象で使わないように
「ごほうびが貰えるから○○をする」という考え方が子どもに定着してしまうと、自分で決めた目的に向かって努力を重ねる、すぐにうまくいかなくても解決策を探して再挑戦するといった、生きていく上で大切なスキル・非認知能力が身に付かなくなります。
ビデオチャットはスマホ使用にカウントされない【ホッとひと息】

同じくスマホや画面の媒体を使いますが、実際に会うことのできない家族とのコミュニケーションの道具としてビデオチャットを利用する場合には、子どもに悪い影響を与えることはないので、ご安心を!

ハッキリしたルールは、子どもにとって成長過程での道標。子どもはまだ自分にとって良いこと/悪いことの判断がつかないので、ルールを決めるのは親の役目です。ルールとのお付き合いを小さい頃に練習しておかないと、社会生活でつまずく原因となりますので、要注意です。
<関連文献>
追記:
東北大学加齢医学研究所のビデオゲームの影響に関する研究論文が掲載されたのは、NatureのMolecular Psychiatry!
私が知らないだけで、日本ではすでに話題になったことなのかもしれませんが、Molecular Psychiatryでアクセプトされたとは、すばらしい!!
私がスイスで知り合った教授たちの中には、自分の論文が掲載されたジャーナルのインパクトファクターを挨拶がわりにお使いになっていた方がチラホラいらっしゃいましたが(一応全員心理学者)、その方たちでさえ平身低頭でお座布団30枚くらい用意してしまうか、嫉妬でメラメラの生き霊を飛ばしてしまうかの(笑)すばらしい功績。
今後の研究グループの活動がとても楽しみですね。
このように意義のある研究が日本で行われ、世界に発信されていることに感激!