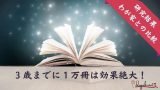2歳児のお子さんへの読み聞かせは、人生で成功するカギとなる非認知能力を伸ばすために最適のメソッド。
読み聞かせをする際、「選ぶ/考える/知る/話す」4つの要素を付け加える読み聞かせ術は、天才児認定を受けた娘が2歳のころ、私が実際に毎日実践していた方法です。
ちょっとした心がけで、読み聞かせの効果をさらに高めることができますので、ぜひみなさんもご家庭でお試しください。
【天才児に不可欠!】非認知能力とは?

非認知能力とは、読み書き・計算などの数値では測れない能力をさします。
引用元:非認知能力 ー 岩手県医師会 (閲覧日:2021年11月5日)
大きく分けて、自尊心、自己肯定感、自立心、自制心、自信などの「自分に関する力」。
そして、一般的には、社会性と呼ばれる、協調性、共感する力、思いやり、社交性、道徳性などの「人と関わる力」です。
どんな才能に恵まれたお子さんでも、非認知能力に欠ける子どもは、人生で成功しません。
生まれつき頭の良いお子さんが、非認知能力がないために「元・天才児」になってしまう悲しいケースを、本当にたくさん身近で体験した私は、断言できます。
子どもの非認知能力は、親が積極的に子どもをサポートしてあげないとうまく伸びないという事実を、すべての親御さんに知ってほしい!と、心から願っています。
2歳児の発達の特徴:読み聞かせで非認知能力が伸びるワケ

2歳児の発達の特徴:
- 自我の芽生え
- 個性が出てくる
- 現実にないものをシンボルとして理解できる
自我の芽生え

「自分」と「他人」は別のものであると、はっきり理解できるようになるのは、2歳のころ。
自分自身を名前や「私」と呼ぶ、または自分のおもちゃなどを「私のもの」と口にするようになります。
お子さんのこのような態度は、「社会性を育てる」準備ができたサイン。
誰かの気持ちに共感する、相手を思いやるといった非認知能力は、自分と他人の区別がつくようになって初めて、効果的に伸ばすことができるのです。
個性が出てくる

自我が芽生えると、「自分の好きなこと」に対する個性が出てきます。
自分の好きなことを、思いっきり自由に探索できれば、それが学びの原動力である探究心に結びつくので、子どもの個性を尊重してあげることは、とても大切です。
現実には見えないものをイメージできる

2歳児になると、お母さんになったつもりで人形にミルクをあげる・ヒーローになったふりをする・おもちゃを別のものに見立てて使うといった「ごっこ遊び」がよく見られるようになります。
「ごっこ遊び」は、子どもが頭の中にあるイメージを反映できるようになったサイン。
1歳のときには、現実に見える「絵」を頼りに情報を集めていた子どもですが、2歳児は読んでもらったお話を頭の中でイメージする想像力を持ち合わせるようになります。
【2歳児】天才児に不可欠な非認知能力を読み聞かせで伸ばす
- 選ぶ:子どもに自分で本を選ばせる
- 考える:読み聞かせた話の内容を考えるきっかけを作る
- 知る:他人の態度・感情・意見のちがいを知る
- 話す:読み聞かせで聞いた内容を親子で話す
【非認知能力の育成】選ぶ:子どもに自分で本を選ばせる
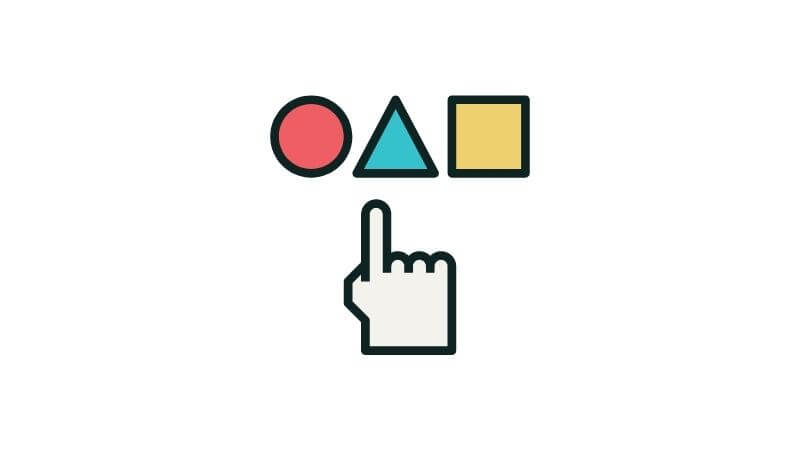
読み聞かせに使う本を、子どもに自分で選ばせることには、一石二鳥のメリットがあります。
自分の好きなテーマやジャンルだと、誰でも夢中になれるので、読み聞かせの時間がさらに充実します。そして、子どもが自分の「好きなこと」を意識するきっかけにもなります。
ドイツの脳科学研究者によると、私たちは1日におよそ2万回も、何かを選びながら生活しているとのこと。a)
でも、どんなに小さな選択でも、自分の好きなこと・したいことを選ぶのって、意外とむずかしくありませんか?
だからこそ、小さいころから「選ぶ」練習を、子どもにさせるのは大切なこと。
自分の好きな本を選ぶことは、ごく小さなステップですが、子どもが「自分で決めていい」という事実は、自己肯定感(自分の好きなことを、親が認めてくれている)、そして自信・自立心(自分で選べる・自分でできる)という非認知能力を、毎日の積み重ねで伸ばす結果につながります。
ただ、まるっきり自由選択だと2歳児はとまどってしまうので、初めのころは例えば2冊の本を見せながら「コレとコレ、どっちがいい?」といった形で、お子さんが自分で選ぶ練習をサポートしてあげましょう。
【非認知能力の育成】考える:読み聞かせた話の内容を考えるきっかけを作る

ただ漠然と読み聞かせをするのではなく、読み聞かせが終わってから、読んだお話の内容について、子どもに質問をしましょう。
「聞く」という受け身の状態を、「考える」という積極的な思考プロセスに移すことで、読み聞かせの効果は何十倍にも広がると私は思います。
何事も、「学び」の体験は「自分で行う」アクティブな状態に転換しないと、実を結びませんからね。
「何がおもしろかった?」という聞き方だと、2歳児初めのころはまだ答えが出てこないと思うので、読み聞かせ本にある「絵」を中心に、質問を開始することをオススメします。
例えば、まず親御さんがいちばんおもしろいと思ったページの「絵」に戻り、「ママは、○○くんのお部屋がカタツムリだらけになっていたのが、おもしろかったわ。あなたは?」と子どもに話を振りましょう。
次第に、お子さんの方から進んで「お話のこの部分がいちばん好きだった」などと話すようになります。
【非認知能力の育成】知る:他人の態度・感情・意見のちがいを知る

物語に出てくる登場人物の態度や気持ちは、バラエティ豊富なので、「自分」と「他人」の区別がつくようになった子どもは、人間の多様性を読みきかせを通じて体験できるようになります。
自分とちがう他人の行いを知ることは、共感力・思いやり・道徳性を育てるために不可欠です。
【非認知能力の育成】話す:読み聞かせで聞いた内容を親子で話す

加えて大切な体験は、読み聞かせ終了後、お話の内容を親御さんと一緒に話し合う時間。
最初のころ、お子さんはなんでも「大好きなママと一緒」が良いので、親御さんが「おもしろかった」と選んだ部分の同じところがおもしろかったと答えるかもしれません。
そんなときには、上で述べた「話を振る」テクニックを用いて、子どもの意見を引き出すお手伝いをしてあげましょう。
例えば、「どこが、なぜ、おもしろいと思ったのか」親御さんの心に浮かんだことを、具体的に言葉にしてあげてください。
すると、読み聞かせ後の質問を繰り返しているうちに、子どもはだんだん、自分の意見を話すようになります。
「自分の意見」と「ママの意見」がちがうことは、悪いことではないと子どもが気づく機会は、非認知能力を育てるため、ひいては心の健康状態にとって、実はとても大事なプロセスなのです。
他人とちがう「自分らしさ」を肯定的に受け止め、かつ自分とちがう他人の気持ちを汲み取り、思いやりを態度で示す能力を持ち合わせる人は、社会の一員として「自分らしさ」を発揮しながら、満足度の高い人生を歩むことができますから。
【天才児への読み聞かせで大活躍】2歳児にオススメの本

2歳児への読み聞かせに使う本は、挿絵とお話の両方が、ほどよい量で調和しているものを選ぶことが大切です。
例えば、わが家では以下の本を使用していました。

お子さんと楽しい読み聞かせ時間をおすごしください!
<参考文献>
a) Ernst Pöppel (2008). Zum Entscheiden geboren. Carl Hanser Verlag München.