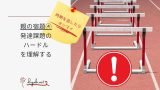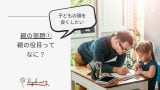「空の巣症候群」という表現には、なんだかおどろおどろしい雰囲気が漂っています。
でも、子どもの巣立ちは通常、突発的に起こることではなくて、いつその時が訪れるのか、予想がつくイベント。そして巣立ちは、子どもが健全に発達している証でもあります。
家が「空の巣」になって、精神的に参ってしまう…と感じる背景に隠された要因と、効果的な対策方法を知ることで、子どもの巣立ちをポジティブに受け止めることができるようになります。
私も実際にこの方法で、「空の巣症候群」にならずにすんでいるので、効果はテキメン♪
【空の巣症候群とは?】典型的な症状

育児と教育に専心していた母親が子供の独立によって虚無感、別離感、孤独感を感じ、うつ状態になることがある。更年期の内分泌的変化も関係する場合もある。
引用元:独立行政法人労働者健康安全機構:職場における心の健康づくり(パンフレット)<セルフメンタルヘルス>
【空の巣症候群の要因】発達段階・ライフステージの変化・喪失三重苦

- ライフステージで次の段階に移るときには、困難がつきまとう
- 時代に伴うライフコースの変化により、「難題への直面」が重複する
- 子どもの巣立ちを見送る親は、あらゆる面で「喪失」と向かい合う
ライフステージで次の発達段階に移るときには、困難がつきまとう

エリクソンの心理社会的発達理論では、ヒトの一生を8つのライフステージに分け、それぞれのステージには独特の「発達課題」があると提唱しています。
乳児期:誕生〜1歳未満
幼児期初期:1〜3歳
幼児期後期:3〜6歳
学童期:6〜13歳
青年期:13〜22歳
成人期:22〜40歳
壮年期:40〜65歳
老年期:65歳以上
ヒトは皆、「まだ自分が体験していない出来事」に直面すると、とまどいます。
ですから、生物学上の発達レベルから次の段階に移行して、年齢特有とみなされる新しい課題、例えば
- ひとりでトイレに行く
- 親と離れて数時間、幼稚園で過ごす
- 集団の一員として、学校で授業に参加する
などにチャレンジするときには、トラブルが発生しやすいのです。
そして、無事に成人したわが子の巣立ちを機に、自分自身の生き方を再構築することは、親世代にとって克服すべき人生の発達課題のひとつだと言えます。
乳児〜青年期にかけて重要な意味を持つ、発達課題に関するテーマは、コチラ↓の記事でご覧ください。
時代に伴うライフコースの変化により、「難題への直面」が重複する

ところで、エリクソンの心理社会的発達理論が発表されたのは、1959年。当時と現在を比較すると、成人期以降のヒトのライフコースそのものが、大幅に変化していますよね。
例えば、
平均寿命:
1950年男性58歳/女性61.5歳
2021年男性81.47歳/女性87.57歳
初婚年齢:
1950年男性25.9歳/女性23歳
2020年男性31.0歳/女性29.4歳
結論として、過去70年間に長寿化・晩婚化が進んだことにより、現代の親世代はライフステージにおいて、「子離れ・更年期・親の介護」という、ヘビーな3つの課題を同時に背負うようになってしまったわけです。
私がもし、1950年代にアラカンだったら、もう天国行きのウェイティングリストに載っているところだわと、冷や汗が…(笑)。
子どもの巣立ちを見送る親は、あらゆる面で「喪失」と向かい合う

子離れ・更年期・親の介護という三重苦に直面する現代社会の女性は、さまざまな点で「喪失感」を鼻先に突きつけられます。
【子どもの巣立ち】
- 未来のある子どもの人生と比べて、自分の人生はすでに折り返し地点に来ている
- 自分の人生で主要な位置にあった母親としての役目が、終わりを告げる
【更年期】
- 閉経により、女性特有の「らしさ」を失う
【親の介護】
- 衰えている親の心身状態に、未来の自分の姿を重ね合わせてしまう
書いているだけで、気分が悪くなってきた。大丈夫か、私(汗)。
皆さんも、この部分で止まっていてはダメ。効果的な対応策をご紹介している次のパートに、さっさとお進みくださいね。
【空の巣症候群】効果的な対処法〜実践中の私からのオススメ

- 空の巣になる現状をポジティブに受け止める:子どもの自立は、健全な成長の証
- 子どもと対等な目線で新しい関係を開始する
- 自由になる時間を自分のためにどう使うか考える
- パートナーとの関係を再認識
【空の巣症候群対策】①空の巣になる現状をポジティブに受け止める

本来、親の役目は子どもの自立を促すこと。
進学・就職、または結婚してもしなくても、ライフステージで「親からの独立」に到達したお子さんは、子どもにとって困難な「健全な自立」という発達課題を、上手くクリアできた証です。
そう考えると、「子どもが巣立ってしまうなんて、寂しくて、悲しい」ではなく、「さすが私の子、すごいじゃない!そして、わが子をここまで育て上げた親の私も、頑張ったわ!」と、子どもが巣から羽ばたいていく現状を、肯定的に受け止められるようになります。
【空の巣症候群対策】②子どもと対等な目線で新しい関係を開始

子どもの自立に伴い、それまで親子間にあった「上下関係」を、見直すことも大切です。
もしすでにお子さんが成人している場合でも、いろいろなことが心配なあまり、親は「あれしなさい・これしなさい」といってしまいがちですが、ちょっと考えてみてください。
「親だから」と、無意識のうちにご自分のお子さんにアレコレ出している指図って、赤の他人には絶対言わない内容じゃありません?
巣立ちの時を迎えるまでに、親と子が丈夫な「愛の絆」で結ばれているのであれば、親の助けを必要とする非常時に、子どもは必ず親の意見を求めてきます。
ですから親は子どもに対して、「あなたなら大丈夫!」という信頼感を、態度と言葉で伝えるべきなのです。
そうすることで、親子が対等な目線に立って、新たな良い関係を築くことが可能になります。
【空の巣症候群対策】③自由になる時間を自分のためにどう使うか考える

時間には限りがあるので、愚痴を言って立ち止まっていたら、もったいない。愚痴は、シワと悩みと性格の嫌なところを増やすばかりなので、さっさとオサラバしましょう。
子どもが巣立ったことで手にする時間は、あなたが自分で好きなように使える、とっても貴重な時間。
時間が手に入るって、ものすごく贅沢なことだから、楽しみましょう♪
- 以前から興味があった趣味に挑戦
- これまで育児で時間が取れなかった昔の趣味を再発見
- 自分のためだけにゆったりとどこかにお出かけ
- 美味しいものをいただく
など、自分が幸せになれることを探し始めたら、楽しくてたまらなくなります。
私は空の巣症候群の予防策として、娘の大学進学と同時にこのサイト・dryukiネットをスタート。また、昔習っていたピアノを再開して、大好きなミステリー小説を読み耽る幸せに浸っています。
私のサイトにたくさんの読者の方が訪れてくださることも、ものすごくウレシイです。私の心のボトックス(まだ顔にもしてないけど)。
【空の巣症候群対策】④パートナーとの関係を再認識

子どものいる家庭で、それまでこなしてきた親の役目から解放されたら、「自分たちはこの後、パートナー同士というつながりだけでお互いの関係を保てるのか」という、テーマに向き合うことも大切です。
長年一緒に生活して、親の役目を共有していたからといって、「相手の気持ちが手に取るようにわかる」なんてカップルは、ほとんどいないのが厳しい現実。
いちばん身近にいるはずのお相手の考えていることって、実はその人の本当の意見からものすごくズレている可能性も大アリなのです。
子どもの巣立ちをきっかけに、お互いに意識して歩み寄らないと、ふたりでいるのに孤独な老後を過ごす、もしくは突如としてお相手から離婚を突きつけられるなんて羽目になりますので、ご注意。
すでにシングルの方にも当てはまることですが、「子どもが巣立った後の自分が、本当に必要とするパートナーとの関わり方って、何かしら?」と意識すればするほど、子どもが巣立った後の人生で、自分にとって大切な「幸せの要素」が見えてくるはずです。
わが家の子離れ実況物語は、コチラ↓の記事でご覧ください。
***************
参考サイト:
厚生労働省 <第2節 結婚に関する意識>(閲覧日2022/09/08)
厚生労働省 <令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数)の概況>(閲覧日2022/09/08)
内閣府 <平均寿命の推移>(閲覧日2022/09/08)
日本経済新聞 <21年の平均寿命、男女とも10年ぶりに短く コロナが影響>(更新日2022/07/29)(閲覧日2022/09/08)